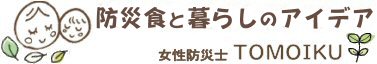Table of Contents
災害後、避難所で食べられる人は一握り
防災の講演で、「災害に対して、備蓄をしていますか?何日分自力で頑張れますか?」という質問を投げかけると、ほとんどの方が不安な顔をします。
災害に備えて食品を備蓄しているという方は、思った以上に少ないのです。
備えていると答えている方も、政府が非常用に3日の準備をするように言っているから…と、いう方が多く、東日本大震災以降、非常用備蓄は最低7日間としています。
発災時、避難所に持ち込む食料が3日は必要であるということです。
実際、東日本大震災では、ライフラインはもちろん、道路や鉄道も寸断され、消防も病院も被災していることや、3日間は人命救助や救援物資を運ぶ道の整備が必要なため3日間は配給がなく、数週間配給がない避難所もありました。
【避難所に届けられた食料】
- 中越地震の時のある避難所:1日1人につき、水は500mlのペットボトルを1本・食事は毎食菓子パン1つ
- 阪神淡路大震災の時のある避難所:水なし1日1人おにぎり1個
- 東日本大震災の時のある避難所:水なし1日1人おにぎり1個
大都市で大規模災害が発生し、壊滅的な状況の場合、救援物資は1か月以上ないと想定して準備することで、家族を守れるのではないでしょうか。
そして、耐震性の高い、マンションや倒壊していない一軒家の場合、避難所に行っても、食料はもらえません。
住む家もなく身体だけの避難をしている方の避難所なので、そのほかの人は「在宅避難」自力で生きていくようにアナウンスしています。

災害発生!
↓
1~2日は避難所で生活(多分、室内には入れない)
↓
落ち着いてきたので「在宅で避難生活」をするように指示される。
テレビで長い列に並んで、配給を受けている人をよく見ますが、それは一握りの人なのです。
災害復旧までの食生活は?今ある食料で生き延びられますか?

電気が通らず、水やガスも止まった状態で、家にある食料と災害用非常食で何日生き延びることができますか?
3日?7日?1か月?…。
人は3日間水がないと生き延びることができません。
水があっても、何も食べないと7日で命が危険です。
1か月経っても、復旧されなかったら…
そんなことあるか!?と思いますか?
もし政府が機能しないほどの主要都市が壊滅状態だったら、十分にあり得ることだと思います。
そのようなことを想像するより、もう1か月以上ストックができるのであれば、準備しましょう。
ストックするものは、半年や1年以上賞味期限が先のモノを準備して、日常で消費をしていくのであれば、数か月の食事の食材は用意できます。
そして、カセットコンロがあれば調理ができます。
そして、水と食材が何日分あるか?…ということです。
非常食や備蓄食というイメージは、何か特別なものを想像する方が多いですが、日常で食べているもので十分非常時でも食事をつくることができます。
市販されている非常食は、避難所に行く際に持参するもので、調理の手間を省くことができる手軽に食べられるもので、救援物資が届かない可能性が高い3日分を用意します。
その後、避難所での生活の許可が下りない方々は、在宅避難・車中・テントでの生活になりますが、その時の食生活は、火元であるガスコンロがあれば生活できます。
【東日本大震災でのライフラインがストップされた報告書】
| 電気の復旧は1週間 当日復旧:10.8% 1日後復旧:52.2% 3日後復旧:78.8% 1週間後復旧:98.6% | ガスの復旧は5週間 当時復旧:0% 1週間後復旧:9% 2週間後復旧:13% 3週間後復旧:42% 4週間後復旧:66% 5週間後復旧:99% | 水道の復旧は3週間 3日後復旧:50% 1週間後復旧:66% 2週間後復旧:88% 3週間後復旧:99% |
30年以内に起こる可能性がある大地震!
もし首都圏が同じようになった場合、東日本大震災よりも月日がかかるとされています。
せめて、1か月分を用意しておきたいところです。
給水車の台数も足りません。
お水の確保は、用意できるものであるならば、1か月分を用意しましょう。
コンロのガスは足りますか?
最悪、サバイバルで火は起こすことができますが、できることならコンロのボンベも1か月分用意しておくといいですね。
そして、食材。
TOMOIKUでは、30日は生き延びることができるよう情報を提供しています。
自分に合ったモノを、備蓄していきましょう。
日常の知恵を非常時に生かす「簡単な30日備蓄と調理法で防災」

自然災害は私達にとって非常時で、日常生活と違うことと考え、非常食の少なさにパニックします。
市販されている非常食に目を向けてしまうので、保存食という価格の高さから、3日分・7日分と少量で済ませられるものであるならば、できるだけ購入したくないと思ってしまいます。
災害時の“食”を日常から切り離してしまうと、生き延びる方法として大きな障害になってしまいます。
非常時だからごちそうを食べたいとか、お腹いっぱい食べたいと思う方はいないでしょう。
きっと、日常の食事がしたいと思うのではないでしょうか。
わざわざ地震のために、準備をすると考えると面倒くさいと感じますし、予算なども考えてしまいます。
そして、備蓄する収納が大変とか、様々な声が上がります。
そして、備蓄を意識すると、地震などの恐怖の瞬間も想像してしまうことから、なかなか迅速に準備ができない心理もあります。
「備蓄しましょう」ということが、心理的負担になることもあります。
まず、水とカセットコンロと鍋!
水とカセットコンロのガスは必ず30日分を用意しましょう。
そして、ローリングストック法で日常で作っている食事の食材で、30日生き延びられるよう、様々なレシピを用意していきます。
非常食だけで30日は過ごすのは大変です。
【常に意識するべき食品30日以上】
詳細はリンク先へ移動します。
- 米は常にストック:災害時の食事 “真空パック5kg のお米”保存方法と賞味期限!魔法の米炊き袋(炊飯袋)が便利
- 乾物用意:乾物の5つの利点と効果|防災食&日常食で取り入れたい
- 缶詰などのたんぱく質:缶詰の5つの利点と効果|防災食&日常食で取り入れたい
- ドリンク類:災害時に便利な様々なドリンク
- 甘いお菓子:災害時だからこそ、心がホッとするものを用意
人は、常に口にしている食事を摂ることで、安心できます。
生きていくことができると感じられるからです。
是非、非常時30日間の食事を、水を無駄にしないで簡単にできる調理法と、日常で食べる食材で作ってみてください。
きっと、その調理法と料理は、日常で食べて慣れ親しんだものになると思います。
最近は部屋を整理するために、食品在庫も少なくしている方もいらっしゃいますが、もし災害が起きた時、行政を頼りにした食品の入手方法は困難であると考えてほしいです。
自分が経験するかもしれない災害状況を想像して、何日分を用意すべきか?と確認してください。
そして、エネルギーや水をあまり使わない調理法を取得しておきましょう!
災害食は「ポリ袋料理・空中料理」の調理法がおすすめ!
最小限の水で防災食を作る方法と注意の記事を用意しています。
まずは、買い物の仕方、食べ方として、ローリングストック法を取り入れましょう。
- 災害時の食生活30日
■ 災害復旧までの食生活はどうなる?簡単な30日備蓄と調理法で防災
■ 被災時の命をつなぐ「食生活」で心を満たすには日常を意識して備える - 食品の備蓄法「ローリングストック法」
■ ローリングストック法(1)救援物資がない!日常備蓄の思考で非常食
■ ローリングストック法(2)食料と日用品の注意点と2つのポイント
■ ローリングストック法(3)備蓄品の分散収納方法!災害を想定し工夫 - 便利な道具
■ 災害時これだけは備えたい「10の役立つ道具」食べるために絶対必要
■ “料理用ポリ袋”選び方と5つの利点-災害時で使う便利な道具で非常食
■ 災害で火や電気がない非常事態!ヒートパックで温かい食事ができる
■ “真空保温調理器”災害時、調理時間と光熱費削減できる便利な調理器具!
■ 災害時の食事 “真空パック5kg のお米”保存方法と賞味期限!魔法の米炊き袋(炊飯袋)が便利
***関連記事***