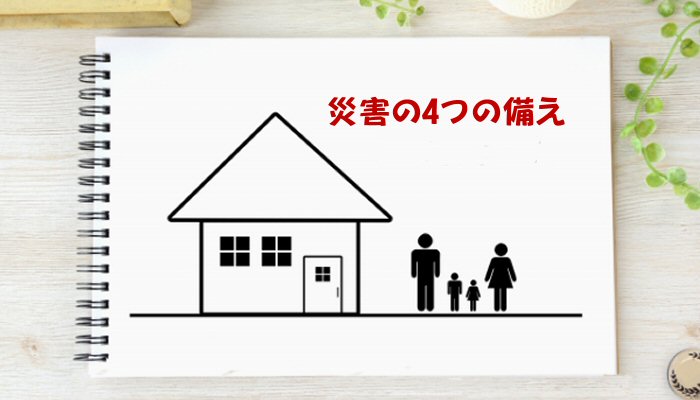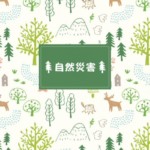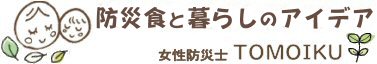Table of Contents
“災害の4つの備え”は日本に住む限りやるべきこと
もしもの時、自分や家族の身を守るのは、あなたの「知識」です。
そして、最低限生活に必要な「備蓄」「道具」
小さなあなたの備えが、大きな助けになります。
災害が起きた後は、たった一言で救われる言葉…「コミュニケーション」が、“安心”という気持ちを生み、復興に力を注ぐことができます。

はじめは、準備で疲れ果ててしまうかもしれません。
しかし、最低限必要な物は、大災害が起きてから後悔しないためにも、今すぐ“災害の4つの備え”の重要な防災アクションをはじめましょう。
そして、4つの備えを終えて、ふだんの暮らしが自然に備えになっているような防災生活を、TOMOIKUでおすすめしています。
自然災害が多い日本に住む限り“災害の4つの備え”は必ず必要です。
地震など自然災害は非常時のことなので、日常生活とは違うと考えがちですが、日本ではどこかで絶えず起こり続けています。
日常生活から切り離してしまうと、私達が生き抜いてうえで、大きな障害になってしまいます。
防災講座やイベントアンケートで「災害に対して、備蓄をしていますか?」と質問をすると、備蓄を備蓄が面倒・備蓄するスペースがないない・備蓄にまわすお金がない・3日分だけ備蓄など、心理的負担が大きい声が多いです。
それは、わざわざ「防災」として購入し準備をしようと思うことから、大変な作業になるのです。
災害時のことを考えるのは気がすすむことではないかもしれません。
しかし、日常生活から、何が最低限必要なものなのか…と考えさせられますし、室内外の環境について…、そしてコミュニケーションの大切さを身にしみて感じると思います。
4つの備え(1)物の備え-救援物資は最低3日はない!

もし、大規模な地震などの災害が起こったら、電気やガス・水道と“ライフライン”がストップされ、被害や物資の供給の停滞が想定されます。
救援物資を運ぶ道が寸断され、避難所への輸送ができず、ヘリコプターで運ばれるなど、私達は東日本大震災で多くの避難生活を見聞きしています。
しかし、経験をしていないため、どうしても震災直後の気持ちから遠ざかってしまうのです。
大規模災害の場合は、消防も病院も被災しています。
助けの手は「ない」と思って過ごすことを覚悟しなければなりません。
自宅の倒壊を免れた人は、発災後も当面自宅で生活していくことが想定されます。
その時は、備蓄で過ごすことになるでしょう。
救援は最低3日は「ない」と考えましょう。
今後予想される「南海トラフ」のような大地震で、応援できる他の都道府県が、他の街を救援出動できるとは限りません。
阪神淡路大震災では避難所に配給が始まったのは3日目で、自宅避難者への配給は6日目でした。
東日本大震災では、交通が遮断され孤立してしまった地域では、配給はもっと時間がかかったのです。
「南海トラフ」によって、大都市である東京・名古屋・大阪に災害が起きた場合、救援で動ける近隣の町は…計り知れない人口の大都市に対して、すべて対応できるでしょうか。
私は30日以上の備蓄が必要と考えています。
それは、高価な非常食を30日分用意するのではなく、ふだん使っている備蓄で食べ繋ぐ方法です。
災害にあったから、特別なモノを食べたいと思うわけではなく、日々食べているものが「美味しい」と思うものです。
そして、生活用品の備えは、ふだんのストックを1か月分と考えておくようにします。
食品や生活用品などは、備蓄から使用してストックする「ローリングストック法」によって、負担なく備蓄ができます。
特別に高価なものを購入して揃えるのではなく、日頃から自宅で生活する上で、必要な物を揃えておくことが、ひとつの不安を取り除くことができる方法で、心理的にもとても重要なことです。
下記記事は「物の備え-救援物資は最低3日はない!」詳しい記事です。
4つの備え(2)室内の備え-転倒・落下・ガラス飛散・移動防止

もしも…自宅でくつろいでいる時、睡眠中に地震が起きたら…。
家具類の下敷きにならないように、転倒・落下・移動防止や、ガラス飛散防止をする必要があります。
ドアが歪んで開けられないことも考えられます。
近年の地震による負傷者の30~50%は、家具類の店頭・落下・移動が原因です。
モノが散らかっていると、移動が困難になりケガのもとです。
部屋にモノを置かないことが最大の防御になるのです。
そして家具などの下敷きにならないように配置することや、その家具に様々な器具で、家具類の転倒・落下・移動防止対策を行うことでリスクを低くすることができます。
下記記事は「室内の備え-転倒・落下・ガラス飛散・移動防止」詳しい記事です。
4つの備え(3)室外の備え-自宅の地形・地質の確認
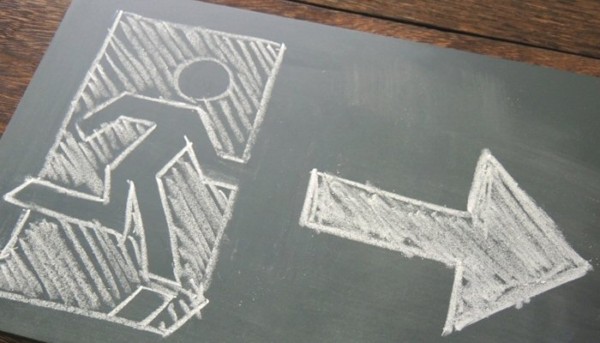
あなたはご近所の地形や地質を把握していますか?
毎日歩いている道ですが、危険な場所などありますか?
家のまわりの地形や地質・崖地・沼地など危険な場所や、過去の災害を調べておくことは、災害対策に必要不可欠です。
そして、あまり歩く道ではなくても、避難場所や避難経路・公民館・広い公園などのオープンスペース・コンビニなどの施設の確認をしておきましょう。
いざという時、どのように動くかということは、とても重要です。
発災時が起きてから調べたり考えたりしていては、自分の命を守るための対応ができません。
何よりも「安全な場所」に避難することができます。
室内だけではなく、室外にも目を向けることは、避難生活になるような場合でも重要なことなので、晴れた日にでも、散歩がてら歩いて確認をしてみましょう。
下記記事は「室外の備え-自宅の地形・地質の確認」詳しい記事です。
4つの備え(4)コミュニケーションという備え

発災時の出火防止や出口の確保など、家族の間で話し合っていますか?
漠然と話をするだけでは、いざというときの役割分担が迅速に行われないまま、時間が経過してしまいます。
そして、外出や登下校中に帰宅困難になったり、離ればなれになった時の安否の確認方法・集合場所も決めておきましょう。
このように家族間では、お互いの命を守り、安否を確認し、その後の行動を「家族のマニュアル」が必要になってきます。
行政が配っている地域の「防災ブック」を活用して決めておきましょう。
そして、普段は挨拶もままならないご近所関係であったとしても、地域の方々とは災害時には協力してく関係になります。
配給のお知らせや、ひとりで暮らしていてもケガや病気になった時、災害時ではご近所さんのお世話を受けることになる可能性もあります。
人間関係が苦手な方は多くいらっしゃると思いますが、日頃から挨拶を交わす関係でいることがとても重要で、避難生活をスムーズにするためにも、ご近所との付き合いの輪を広げておきましょう。
下記記事は「コミュニケーションという備えの」詳しい記事です。
「4つの備え」まとめ

最低限必要な「4つの備え」は、いつかやろう…と思っていても、何かきっかけがないと後回しになりがちです。
漏れた事柄があるかもしれません。
是非、チェックをしてみてください。
- 物の備え
発災時に何より必要なのが、食料品と生活必需品の備えをしておきましょう。 - 室内の備え
家具類の下敷きにならないための、転倒・落下・移動防止・ガラス飛散防止対策をしましょう。 - 室外の備え
安全に避難するために、家のまわりや通勤通学の道などの状況や危険度を調べておきましょう。 - コミュニケーションという備え
災害時には近隣の住民同士の協力が不可欠です。家族や近所の方とのコミュニケーションをとるようにしましょう。
4つのポイントはしっかりとおさえて、今からでもできることを各コーナーでチェックシートを用意していますので、ひとつひとつ確認しましょう。
はじめに
■ 地震対策でやること“災害の4つの備え”救援物資は最低3日はない!
- 物の備え
■ 「防災の日」災害被害0次から3次とレベル別に用意するものリストと避難方法を確認!
■ ローリングストック法(1)救援物資がない!日常備蓄の思考で非常食
■ ローリングストック法(2)食料と日用品の注意点と2つのポイント
■ ローリングストック法(3)備蓄品の分散収納方法!災害を想定し工夫
■ 自然災害で最低限必要なモノを確認・用意していない人は自己責任で! - 室内の備え
■ 地震防災「室内の備え」3つのポイントと転倒・落下・移動防止方法 - 室外の備え
■地震防災「室外の備え」3つのポイントで安全な避難経路を確認 - コミュニケーションという備え
■地震防災「コミュニケーションという備え」家族会議と地域との関係