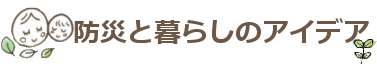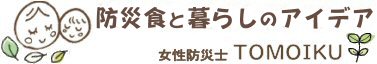防災用品点検の日は、3月1日・6月1日・9月1日・12月1日と年に4回あります。
用意している防災用品を見直しをすることが目的です。
季節によって防災用品は変わります。
日本は自然災害が多い国ですし、季節によって用意するべき物が違うので確認することが必須!
そして、定期的に防災意識を高めておくのも大切です。
Table of Contents
3月1日「防災用品点検の日」大災害心がまえを!未来ある子供たち

2011年(平成23年)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震およびこれに伴う福島第一原子力発電所事故による大災害から10年。
あの光景は、今でも忘れることができませんし、忘れてはいけないことです。
東日本大震災で発生した津波の最高到達点は、30m…ビルで10階の高さでした。
ハワイのような波打つイメージとちがい、大きな壁が海から押し寄せてくる黒い津波…そして街を…家を…人をのみ込んでいきました。
津波の水は、単純な水ではなく、町を破壊し人をのみ込んだ黒い水です。
海から遠い地域までのぼっていく、水のエネルギーは凄まじいものでした。

普段の生活を思い返してみると、私たちは食べたい時に食べ、飲みたい時に飲める…遊びたい時は自由に遊び、温かい布団で体を休めることができるような豊かな国で暮らしています。
しかし、大災害が起きることで、どれだけの苦しみ…どれだけの悲しみ…そしてどれだけの不自由を味わうのでしょう。
そんな状況下では、食べられること、安心して眠りにつけることが“当たり前”ではなくなるのです。
避難生活を「健康」に過ごすことは、奇跡になるのかもしれません。
防災士の講習で、今後起きるであろうと言われている南海トラフや首都圏直下型の地震は、東日本大震災の被害の何倍も大きい災害になると言われています。
大災害の時、命を守ることができ、自宅避難をすることになるのはまだよいのかもしれません。
自分の周りが無事であっても、広範囲で物流が止まり、現在自由に入手できるものは手に入れることができなくなるでしょう。
私のように子どもを育て上げ、歳を重ねている者は、今後30年の間に起きる可能性の高い大震災は経験しないままでこの世を去るのかもしれません。
しかし、毎日が楽しくて仕方がないと言わんばかりの笑顔の孫達をみていると、きっとこの子達は大震災を経験し、恐怖や悲しみで泣き叫ぶことを経験するのだろう…と…。
どうか、生き延びてほしい…と思うのです。
そして、現在健康に過ごしている小さな子達…未来の子供たちに、しっかりと成長できるものを用意してあげたいと思うのです。
その準備をするのは、大人です。親です。自分自身です。
行政は何もできない…機能しないほどの大災害を想定してみてください。
大災害になり数か月間、配給が成されない状況でも、子どもたちにはしっかりと食べる物の準備をしてあげてほしい。
戦後を想像してほしいのです。
国民すべての人達が、自宅避難の食べ物を数か月分用意していることで、家を無くして避難所にいる人達に、食べ物が多く配給される確率が高くなるのです。
自分は自宅避難になるのかもしれない…でも、避難所生活を余儀なくされるのかもしれない。
ですから…「どうにかなる」…という行政や他人任せの考え方を、災害に関しては捨ててほしいと切に願います。
3月1日「春の防災用品の点検」で注意すること

非常用の袋などの点検はもちろんですが、3月の点検は、新年度による会社や学校などの移動、引っ越しなどがあるため、通勤通学時に使用する経路で危険な場所の点検や、引っ越し先による避難所などの確認を必ず行いましょう。
春は季節の変わり目であることや、新年度による精神的負担が大きいので、体調を崩すことも多く、非常用袋の中に腹痛や下痢止め・頭痛など、自分で体調不良になりやすい部位の薬を用意しておくといいでしょう。
体調不良になったら、非常用袋から薬を取り出せばよいので、わざわざ非常用として薬を購入する必要はありません。
冬のために用意した厚手の暖房着は不要となりますが、まだまだ寒暖差がある季節でもあるので、温度調節ができる薄手の上着やカーディガンは用意しておきましょう。
衣替えと同じく、非常用も衣類などの確認をします。
そして、食品などの賞味期限の確認です。
非常用袋の中は、非常食を利用している方が多いと感じますが、まだまだ賞味期限まで余裕があると思っていた食品が、そろそろ期限が迫っていることがあります。
一度にすべてを揃えるのは金銭的負担になるため、次回の「防災用品の点検」6月1日までに少しずつ入れ替えるような気持ちで、用意しましょう。
買い足しでおすすめなのは、避難所で野菜不足が深刻な問題を引き起こすため、粉末の野菜ジュースや青汁などを用意するのがおすすめです。
「防災用品の点検」4段階に分けて準備するのが基本

3月1日「防災用品点検の日」は、冬物から春物に切り替えます。
次回の防災用品点検日は6月1日なので、夏物は次の点検で用意します。
そして、防災用品は、3段階に分けて準備するのが基本です。
| 名称 | 説明 | 備え方 |
|---|---|---|
| 0次の備え | 最低限の非常用品 | 常に身につける携帯用防災グッズ |
| 1次の備え | 災害発生後直後、人命確保を優先で、3日間に避難所などの自宅外で安全な場所に避難するための持ち出し品 | 3日分の非常用持ち出し袋 |
| 2次の備え | ライフラインの復旧までに少なくとも7日間、救援物資が届くまでの避難生活に必要な備蓄品。1週間分(できれば2週間以上の食料や生活用品) | 自宅に備蓄して、避難所に持ち出すもの |
| 3次の備え | 避難生活が長期間になることを想定して、物流が止まり物の入手が困難になった場合の対策をする。数週間から数か月 | 長期にわたる自宅避難 |
防災用品点検:0次の備え常に所持しているもの

0次の備えは、常に所持しているものなので、コンパクトにする必要があります。
100円均一で揃えられるようリストを用意しています。
ハンカチ・ティッシュ・風呂敷・絆創膏・携帯グッズ・裁縫セットは100円均一で揃えています。
そして、食べ物として甘いアメひとつでも、一時の空腹をしのげるものですし、できることならバランス栄養食を1個持っているといいでしょう。
防災用品点検:1次~3次避難段階別リスト

避難用として準備する内容は、3日とも7日とも言われています。
しかし、持ち出すものが多くて手間取ってしまうことなど本末転倒であり、まずは1回で避難所に移動することができる量として3日分の用意が必要ということです。
そうと言っても、飲料水だけでも重いため、荷物の入ったリュックサックは背負って確認しておきましょう。
高齢者や子供は3日分の食料を自分で背負うことは、できないと想像します。
我家は90歳の高齢者から5歳の孫までいますが、安全に避難所に移動させるだけでも大変です。
家族で防災用品点検と共に、話し合っておくことが重要です。
コミュニケーションも必要な備えです。
次のページは「1次から3次の3段階の防災用品リストページ」をまとめています。
はじめに
■ 地震対策でやること“災害の4つの備え”救援物資は最低3日はない!
- 物の備え
■ 「防災の日」災害被害0次から3次とレベル別に用意するものリストと避難方法を確認!
■ ローリングストック法(1)救援物資がない!日常備蓄の思考で非常食
■ ローリングストック法(2)食料と日用品の注意点と2つのポイント
■ ローリングストック法(3)備蓄品の分散収納方法!災害を想定し工夫
■ 自然災害で最低限必要なモノを確認・用意していない人は自己責任で! - 室内の備え
■ 地震防災「室内の備え」3つのポイントと転倒・落下・移動防止方法 - 室外の備え
■地震防災「室外の備え」3つのポイントで安全な避難経路を確認 - コミュニケーションという備え
■地震防災「コミュニケーションという備え」家族会議と地域との関係
- 災害時の食生活30日
■ 災害復旧までの食生活はどうなる?簡単な30日備蓄と調理法で防災
■ 被災時の命をつなぐ「食生活」で心を満たすには日常を意識して備える - 食品の備蓄法「ローリングストック法」
■ ローリングストック法(1)救援物資がない!日常備蓄の思考で非常食
■ ローリングストック法(2)食料と日用品の注意点と2つのポイント
■ ローリングストック法(3)備蓄品の分散収納方法!災害を想定し工夫 - 便利な道具
■ 災害時これだけは備えたい「10の役立つ道具」食べるために絶対必要
■ “料理用ポリ袋”選び方と5つの利点-災害時で使う便利な道具で非常食
■ 災害で火や電気がない非常事態!ヒートパックで温かい食事ができる
■ “真空保温調理器”災害時、調理時間と光熱費削減できる便利な調理器具!
■ 災害時の食事 “真空パック5kg のお米”保存方法と賞味期限!魔法の米炊き袋(炊飯袋)が便利
***関連記事***