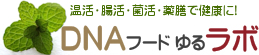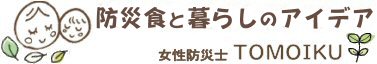新型コロナウイルスの予防は、何よりも人と接触しない自粛行動が必要です。
そして、外出したら、必ず手洗い!必ずうがい!
それは、インフルエンザでも同様な予防方法です。
しかし新型コロナウイルスとインフルエンザでは、感染レベルが違います。
“ウイルスに対抗できる”という視点から、緑茶や紅茶によって少しでもウイルスに対抗できる可能性があるのであれば、体にとって害になることがない方法で、しかもお金もあまりかからないのだから、やってもいいのではないか…と思うのです。
もうすでに「緑茶や紅茶」のうがいをご存じの方は、「正しいうがいの予防法」を、確認してみてください。
Table of Contents
緑茶・紅茶はウイルス感染症予防に効果的!新型コロナウイルス対策は?
緑茶や紅茶のうがいは、ウイルス感染症予防に効果的という科学的な裏付けがあるようです。
のどのウイルスに対抗するために、医薬品である「うがい薬」はもちろん、菌やウイルスを殺してくれるとのことですが、一方で、私たちのノドを守るために必要な常在菌まで殺してしまうリスクがあり、「うがい薬」を使ったら悪化した例は多くあります。
水でうがいすることでも、十分に効果はありますが、食品に含まれる抗菌作用などの有効成分によって、ウイルスや細菌を除去したり殺菌したりする効果も高まります。
食品には、抗菌作用だけではなく様々な効能がありますが、「本当に効果あるの?」と疑問視してしまうのも確かです。
そして、インフルエンザと新型コロナウイルスでは、また状況も違います。
しかし、緑茶や紅茶のウイルス対策は科学的根拠を確認すると効果が見えるであることから、新型コロナウイルスでも、全くのゼロの可能性ではないような気がします。
ウイルスの侵入経路「粘膜」強化と予防

緑茶と紅茶に関しては、研究による結果の「エビデンス」があります。
インフルエンザウイルスの一番の侵入経路は、粘膜です。
ノドなどの粘膜は、外気と直接触れていることから、インフルエンザや新型コロナウイルスに限らず、吸い込んだ菌やほこり・カビなどが付着しやすく、物理的にうがいなどで汚れを洗い流すことで、口腔やノドを清潔に保つことができます。
新型コロナウイルスもインフルエンザ同様、目や鼻・口からの感染が報告されています。
インフルエンザの予防は、目や鼻・口などの粘膜の乾燥を防ぎ、粘膜上から異物を排除する繊毛の働きを高めるという点で、うがいは予防対策になっています。
ウイルスは、いったん体内に入ってしまうと「うがい」での効果がありません。
うがいは、あくまでも体内にウイルスが入ってしまう前の予防として、日々の習慣にすることが大切です。
新型コロナウイルスに対抗できるエビデンスではありませんが、ノドに付着するウイルスを相手に対抗するという視点で「うがいの予防」を紹介していきます。
でも、うがいの効果を過信してはならず、風邪のウイルスに予防効果があることは実証データがありますが、強力なウイルス「新型コロナウイルス」に対してのエビデンスは、まだありません。
そのため、粘膜そのものを潤したり高めたりするための食生活も必要となります。
粘膜を潤す食事については姉妹サイトで紹介しています。
関連サイト:新型コロナウイルスの予防の食事について
緑茶の効果|ウイルスに対抗するというエビデンス

インフルエンザウイルスは、鼻やノドの中に入り込んで増殖して、症状を引き起こします。
ノドにウイルスの侵入や増殖を抑えられるように「うがい」をしますが、「水より緑茶でうがいをした方がインフルエンザ感染予防効果が高い」との成果を、2006年、静岡県立大学の研究グループが高齢者を対象とした実験を行い発表しています。
しかし、高校生を対象にした実験では、1日3回程度のうがいでは回数的に足りないという結果も出ています。
ウイルスは比較的短時間で細胞内に侵入するので、1日数回のうがいでは洗い流せないのかもしれません。
どうも、20分でウイルスは体内に侵入するようです。
緑茶がお勧めなのは、お茶を積極的に毎日飲むことがインフルエンザの予防に有効であることが知られているからです。
ノドの粘膜を潤し、ウイルスを侵入前に洗い流す目的なら、うがいの後に吐き出さずに飲み込んでも良いはずという論理です。
胃に入ってしまえば、インフルエンザウイルスは胃酸で退治できると言われていますが、これも「新型コロナウイルス」では、はっきりしたエビデンスはありません。
まだ研究途中といったところです。
緑茶に含まれる“カテキン”には強い殺菌作用・抗ウイルス作用があるからです。
カテキン類のエピガロカテキンガレート(EGCg)は、少量でウイルスの増殖を強く抑制します。
緑茶をこまめに飲むことで、体内への効果として、殺菌作用・抗ウイルス作用を期待してもいいのではないでしょうか。
通常のうがいと違って、緑茶を水筒で持ち歩いて、ウイルスがノドに付着して体内侵入するであろう経過時間の20分おきに緑茶を飲む…という予防対策でもいいと思います。
緑茶を20分おきにひと口飲むという予防法は、一部のお医者さんの間で行われているとのことです。
参考資料:静岡県立大学薬学部 エビデンス:新型インフルエンザウイルス感染抑制効果 https://release.nikkei.co.jp/attach_file/0497575_02.pdf
紅茶の効果|ウイルスに対抗するというエビデンス
紅茶に含まれる、紅茶ポリフェノール“テアフラビン”が、インフルエンザウイルスやその他のウイルスを短時間に無力化する、というエビデンスがあります。
紅茶(発酵茶)のテアフラビンは、緑茶に含まれるカテキンという成分が醗酵過程で変化したものです。
テアフラビンは、インフルエンザウイルスの生きた細胞に対する吸着能力を失わせるため、すべての種類のウイルスに効果が認められるとのこと。
インフルエンザウイルスの感染性を10秒で、100%失わせることの出来る紅茶の濃度は、市販の紅茶を使った実験では通常飲む紅茶の 5 分の 1 の薄さで十分でした。
参考資料:国立予防衛生研究所ウイルス部などのエビデンス:紅茶エビデンスによるインフルエンザウイルス感染性の阻止 http://journal.kansensho.or.jp/kansensho/backnumber/fulltext/68/824-829.pdf
緑茶カテキンにも同様の効果はあるのですが、紅茶の方が感染防止率が高いのはないか…とも言われています。

ウイルスを流す「正しいうがい予防法」

うがいは、ノドの場所ごとに分けて順番にうがいをするのが正しい方法で、ノドの入り口をガラガラ~としただけでは、汚れがきれいに取れません。
水を緑茶や紅茶を5倍に薄めてうがいをすると、抗菌効果がアップする可能性があるので、実践してみましょう。
※下記のうがい方法は、水を基準に書いていますが、水を緑茶や紅茶に置き換えてください。
- うがいをする(ブクブク)
口の中は細菌がいっぱいなので、口の中に水を含み、唇を閉じてから頬を左右に動かしてブクブクと動かし、食べカスや粘液を落とします。 - 喉をうがいする(ガラガラ)
もう一度口の中に水を含み、上を向いてノドをガラガラ…この時に「オ~」と声を出すと口蓋垂の奥まできちんと洗えてうがいの効果を高めることができます。
口の中の水がぬるくなったら、水を吐き出し2~3繰り返します。 - 口をすすぐ
仕上げに口の中のpHを元に戻すために、水で口をすすぎます。
子供や高齢者がうがいをする時は、誤嚥(ごえん)に注意しましょう。
それ以前に、うがいで「洗い流す」ことも重要ですが、ウイルスを喉や鼻の粘膜に付けないようマスクの着用などで心がける予防はしっかり行いましょう。
ウイルスに対抗する様々な対策を!

風邪などのウイルスから身を守るための予防策はいろいろとあります。
緑茶や紅茶でうがいすることで、ウイルスに対抗できる効果を上げることができるかもしれません。
うがいをする習慣の他に、抗菌作用がある緑茶や紅茶を、のどを潤すために短時間(20分おき)で少量を飲むこと。
そして、最も有効なのは、免疫力をあげ、ウイルスへの抵抗力を高めることです。
免疫力の高い人は、もしウイルスに感染しても、自力でウイルスを追い出すチカラを持っていて、発症のリスクが低下しますし、もし発症しても重症化せず回復することができます。
免疫力を高めるためには、日ごろから規則正しい生活・質の良い睡眠をとることと、栄養バランスの良い食事を心がけることが大切です。
新型コロナウイルスが終息するその日まで…そして、これから新型コロナウイルス以上に強いウイルスが現れるのかもしれないという意識を持って、ウイルスに対抗できる対策は「習慣化」して、自分の体をウイルスに対抗できるカラダに仕上げておきましょう。
当ブログの姉妹サイトでは、「免疫力を高める食材」も紹介している「DNAフードゆるラボ」がありますので、是非参考にしてください。

- 食品の備蓄法「ローリングストック法」
■ ローリングストック法(1)救援物資がない!日常備蓄の思考で非常食
■ ローリングストック法(2)食料と日用品の注意点と2つのポイント
■ ローリングストック法(3)備蓄品の分散収納方法!災害を想定し工夫 - 備蓄の栄養
■ 災害時「栄養不足にならない備蓄方法」簡単バランス非常食料30日分
■ 災害に備える30日分!栄養が偏らない効率の良いストック法とは - 備蓄食品の利点
■ 防災食は何を何日分どう備蓄?日常食で30日備える5つのポイント
■ 【粉もの】災害時の救世主「粉もの」コーナー
■ 【乾物&フリーズドライ】災害時不足する食材を補える「乾物」のコーナー
■ 【缶詰】防災食&日常食で取り入れたい「缶詰」コーナー
■ 【レトルト】災害時の備蓄用非常食「レトルト食品」コーナー
■ 【乾麺】手軽で主食になる「乾麺」コーナー - 自家製の乾燥物
■ 天日干し野菜はムダなく旨味が凝縮!災害時の野菜不足を乾燥野菜で補う調理方法 - ローリングストック法で備えておきたい便利な食材
■ 【主食になるもの】米や麺類だけはなく、主食の代替食コーナー
■ 【食材になるもの-魚・肉・たんぱく源】普段食べているものだけど、備えておきたい食材コーナー
■ 【食材になるもの-野菜・海藻類など】乾燥野菜をはじめ、用意しておくと便利な食材コーナー
■ 【味付けになるもの】災害時、便利な味付けになる食材などのコーナー
■ 【乳製品】災害時は乳製品が入手できなくなるので代替品を紹介コーナー
■ 【嗜好品】果物やお菓子など災害時に栄養に結びつくモノコーナー
■ 【調味料】備えておくことで便利で日持ちする調味料のコーナー
■ 【飲み物】災害時だからこそホッとできる1杯のドリンクを備えるコーナー - 市販の非常食
■ 【非常用のご飯】備えて便利な包装米飯!非常食の5年間長期保存と数か月のパックご飯
■ 【非常用の水】水の賞味期限と備蓄「長期保存水とミネラルウォーター」どちらがいい?
■ 【非常食アレンジ】カンパンを備えるか?賞味期限切れ前に5つの料理方法で食べた
■ 【非常食定番】防災対策に非常食「氷砂糖」を備える理由と体に与える3つの利点
■ 【災害準備】コストコと100均で非常食用意!水だけでできるパスタ
■ コンビニと100均のお菓子が外出先で災害時の備えに!バッグの中の非常食!心得サイト
■ 【非常主食・ごはんやレトルトカレー・味飯】安全で主食になる食料コーナー
■ 【非常食汁物】備えるのに必要「汁物」コーナー
■ 【非常食主菜】そのまま主菜として食べられる「主菜」コーナー
■ 【非常食副菜】体のバランスを整える「副菜」コーナー
■ 【非常食お菓子】大人から子供まで備えたい「お菓子」コーナー
■ 【非常用ドリンク】災害時だからこそ備えたい「飲み物」コーナー
■ 【非常食健康食品】災害時の栄養不足を補う備え「健康食品」コーナー - 防災料理のアイデア
■ 災害食「ポリ袋料理・空中料理」最小限の水で防災食を作る方法と注意
■ 災害時「警視庁おすすめ水漬けパスタ法」他の乾物でも代替!ローリングストック法アイテム
***関連記事***
![]()